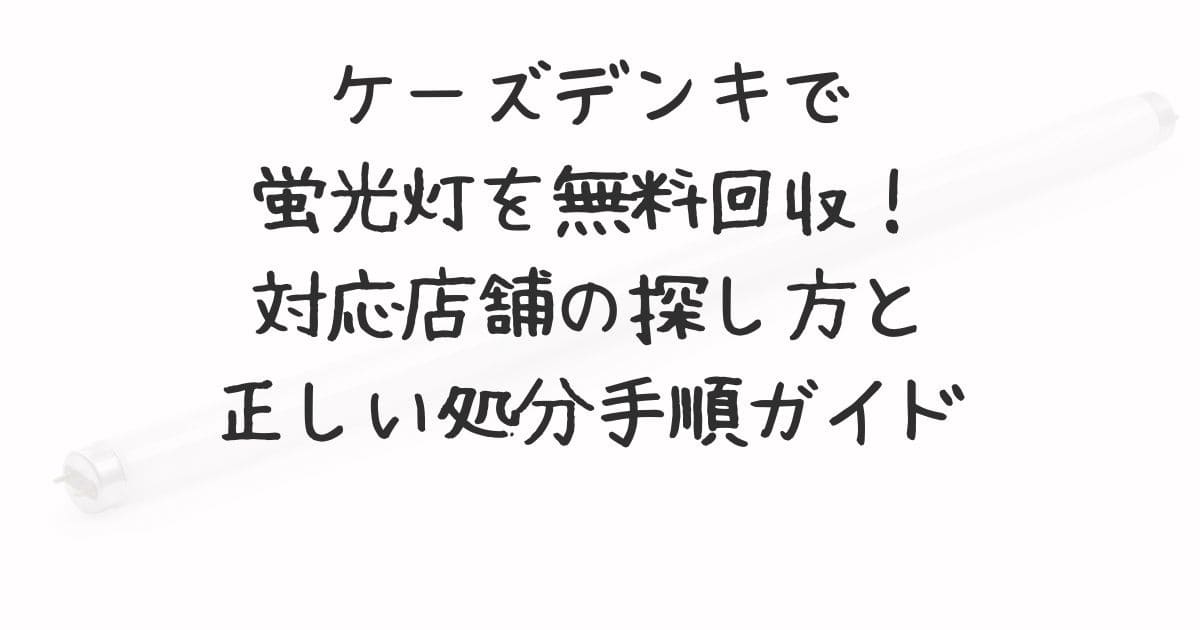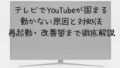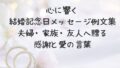蛍光灯ってそのまま捨てられないの?
おうちで使っていた蛍光灯、取り替えたあとはどうしていますか?
実は、蛍光灯には”水銀”が含まれているため、普通の家庭ごみとして出すことができないんです。
うっかり捨ててしまうと、環境への悪影響だけでなく、地域によっては罰則の対象になることも。
また、よく似た形の電球やLEDとは処分方法が異なるので、きちんと確認してから処分することがとても大切です。
ケーズデンキの蛍光灯回収サービスとは

ケーズデンキでは、一部の店舗で使用済みの蛍光灯を無料で回収してくれる便利なサービスがあります。
対象となるのは、直管型や丸型といった、ご家庭でよく見かける一般的な形状の蛍光灯です。
これらは比較的持ち運びやすく、回収ボックスにも入れやすいので処分がスムーズに進みます。
ただし、破損してしまった蛍光灯や、事業用などの大型タイプについては、安全面や保管の都合から回収の対象外となる場合が多く見られます。
そのため、持ち込む前に、対象かどうかを電話やウェブサイトでしっかりと確認しておくことが安心につながります。
さらに、店舗によってはスタッフによる有人対応ではなく、店内に設置された専用の回収ボックスを利用する形式となっていることもあります。
このような場合は、入口付近やサービスカウンター近くなど、目立つ場所に設置されていることが多いですが、中には受付カウンターで声がけをする必要がある店舗も存在します。
対応が店舗ごとに異なるため、訪問前に各店舗のルールを事前にチェックしておくと、迷わずスムーズに手続きができます。
回収ボックス設置店舗の調べ方【3ステップ】

- 公式サイトで確認:ケーズデンキの公式サイトには便利な店舗検索機能があります。地域ごとに絞り込み検索ができるため、お住まいの近くに対応している店舗があるかどうかをすぐに確認できます。「蛍光灯回収」「リサイクル」などのキーワードを入力して検索すると、該当店舗の情報が表示されます。また、各店舗ページには営業時間やサービス内容が掲載されているので、訪問前の参考にもなりますよ。
- SNSや口コミをチェック:Twitter(X)やGoogleマップなどの口コミサイトには、実際に蛍光灯を持ち込んだ方の体験談が多く投稿されています。「〇〇店で蛍光灯の回収ボックスを見つけた」「カウンターでお願いしたら丁寧に対応してくれた」などの具体的な声を参考にすると、より安心して店舗を訪れることができます。SNSの検索機能を使って「ケーズデンキ 蛍光灯 回収」などのワードで調べてみるのがおすすめです。
- 店舗へ電話で問い合わせ:どの方法よりも確実なのが、店舗への直接の問い合わせです。電話で「使用済みの蛍光灯を持っていきたいのですが、回収していただけますか?」と丁寧に尋ねると、回収の可否や対応方法、持ち込み時間などの詳しい案内をしてもらえます。ついでに、回収ボックスの場所や混雑しにくい時間帯なども聞いておくと、よりスムーズに処分ができますよ。
実際に設置されている店舗の紹介

たとえば、埼玉県の「吹上店」や、青森県の「八戸店」では、実際に回収ボックスの設置が確認されています。
これらの店舗では、比較的アクセスしやすい場所にボックスが設けられており、お買い物のついでに気軽に利用できるのが特徴です。
中には、入口近くの目立つ場所に設置されていることもありますが、逆にサービスカウンターの横や壁際など、少し見つけにくい位置に置かれている場合もあります。
そのため、店員さんにひと声かけて場所を教えてもらうのも安心です。
また、店舗によって設置状況や運用方法が異なるため、同じケーズデンキの看板でも対応が統一されているとは限りません。
ある店舗では積極的に回収を行っていても、別の店舗では実施していないケースも珍しくないのです。
特に、地方店舗や大型店・小型店で対応が分かれることもあるため、やはり事前の確認はとても大切です。
ウェブサイトだけでなく、実際に問い合わせてみることで、より正確な情報を得ることができますよ。
蛍光灯の安全な持ち運びと梱包のコツ

蛍光灯は繊細なガラス製品なので、少しの衝撃でもパリンと割れてしまうことがあります。
持ち運ぶ際には、新聞紙やプチプチで包んで衝撃を和らげ、その上から段ボール箱などのしっかりした容器に入れておくとより安心です。
袋だけでの持ち運びは避け、できるだけ固定できる箱を選ぶのがポイントです。
特に、小さなお子さんがいるご家庭やペットを飼っているおうちでは、割れたときのリスクを考慮して慎重に準備を進めることが大切です。
床に置きっぱなしにせず、高い場所や手の届かないところに一時的に保管する工夫もあると安全性が高まります。
もしも運んでいる最中や保管中に誤って割れてしまった場合には、掃除機を使うのは避けてください。
細かいガラス片や水銀が飛散するおそれがあるため、必ずマスクをつけて、換気をしながら新聞紙や厚紙を使ってそっと集めましょう。
片付けが終わったあとは、自治体が定めている方法に従って、破損物として処分してください。必要に応じて自治体へ相談するのもおすすめです。
持ち込みに適した時間帯と曜日は?

お店が混雑しやすいのは、やはり土日や平日の夕方の時間帯です。
特にお仕事帰りの時間帯や週末は来店客が多くなる傾向があり、受付カウンターやレジ周辺が混雑することもあるため、できるだけ避けるのがスムーズです。
比較的空いているのは、平日の午前中やお昼前後などの時間帯。
こうした時間に訪れることで、店員さんにゆっくり相談できたり、回収ボックスの場所を聞いたりするのもスムーズになります。
また、混雑していないと落ち着いて行動できるので、慣れていない方でも安心して処分作業を行うことができますよ。
加えて、雨の日は足元が滑りやすくなるため、転倒などのリスクも少し高くなります。
そんなときは、蛍光灯を新聞紙やプチプチで包んだうえで、ビニール袋や丈夫な手提げ袋に入れて持ち運ぶと、雨による水濡れや滑りの対策にもなって安心です。
さらに、買い物のついでに蛍光灯を持ち込めば、わざわざ別日に足を運ばずに済むので、時間の節約にもなります。
「今日のついでに処分しておこう」と思える気軽さが、習慣として続けやすいポイントかもしれませんね。
ケーズデンキの環境施策と回収サービスの位置づけ

ケーズデンキでは、蛍光灯の回収だけでなく、省エネ家電の販売や、使わなくなった家電のリサイクル回収にも力を入れています。
環境保護への意識が高く、リサイクル活動の一環としてこのサービスが行われています。
他の家電量販店(ヤマダ電機やジョーシンなど)でも同様の取り組みがありますが、店舗ごとに対応状況が異なるため、比較しながら選ぶのもひとつの手です。
近くに対応店舗がないときの代替手段

近所に蛍光灯回収対応のケーズデンキがない場合は、以下のような代替手段を検討してみてください:
- ホームセンター(カインズ・コメリなど):一部店舗で回収実施中。
- 自治体指定のリサイクル拠点:地域の清掃工場やクリーンセンターなど。
- 郵送・宅配リサイクル:環境省や企業が提供する有料サービスも。
蛍光灯を無料で処分するための流れ【初心者でも安心】

- お住まいの自治体や最寄り店舗の回収情報をチェック
- 回収可能かどうかを店舗に電話で確認
- 割れないように梱包して、安全に持ち込む
この3ステップを押さえておけば、初めての方でも安心して処分できますよ。
よくある質問Q&A|蛍光灯回収のお悩み解決

- Q:LEDや白熱電球も一緒に回収してくれる?
→ ケーズデンキでは基本的に蛍光灯のみが回収対象となっており、LED電球や白熱電球など、形が似ていても別の種類の照明器具は対象外であることがほとんどです。これらについては、各店舗によって取り扱いが異なる可能性があるため、訪問前に電話で確認しておくと安心です。地域や時期によって、期間限定で他の照明器具も回収対象になっている場合もあるため、公式サイトの情報もチェックしてみるとよいでしょう。 - Q:割れた蛍光灯は回収してもらえる?
→ 割れてしまった蛍光灯は、安全面の配慮から回収の対象外としている店舗が多いのが現状です。ガラス片の飛散や水銀の漏れといったリスクがあるため、通常の回収ルートでは対応できないことが理由です。そのため、割れてしまった場合には、お住まいの自治体のごみ処理ガイドラインをよく確認し、破損物として適切に処分しましょう。自治体によっては専用の回収日や持ち込み先を指定していることもあります。 - Q:何本まで持ち込めるの?
→ 基本的には明確な本数制限を設けていない店舗が多いですが、一度に大量の蛍光灯を持ち込むと、回収ボックスがすぐに満杯になってしまう恐れがあります。家庭で出た数本程度であれば問題ありませんが、引っ越しや事業で大量に不要になった場合などは、事前に店舗へ相談しておくことをおすすめします。場合によっては、対応を分けて持ち込むよう依頼されることもあります。
自治体別・蛍光灯回収の対応状況

東京23区では、区によって蛍光灯の回収方法が異なります(例:練馬区は資源回収、板橋区は持ち込み制など)。
大阪や名古屋でも市によってルールが違うため、公式サイトを確認してから動くと安心です。
実際に利用した人の口コミ・体験談
「想像よりずっと簡単でした」「店員さんが親切で安心した」「この店舗は回収してなかったので注意!」など、SNS上には実際の声がたくさんあります。
困ったときは、X(旧Twitter)やInstagramで「ケーズデンキ 蛍光灯 回収」と検索してみるのもおすすめですよ。
まとめ|ケーズデンキを賢く使って、蛍光灯を無料・安全に手放そう
蛍光灯の処分は少し手間に感じるかもしれませんが、環境に配慮しながら無料で行える方法がたくさんあります。
まずはお住まいの地域の情報と、お近くのケーズデンキの対応状況を確認してみましょう。
少しの工夫で、手間なく、安全に、そしてエコにつながる行動ができますよ。