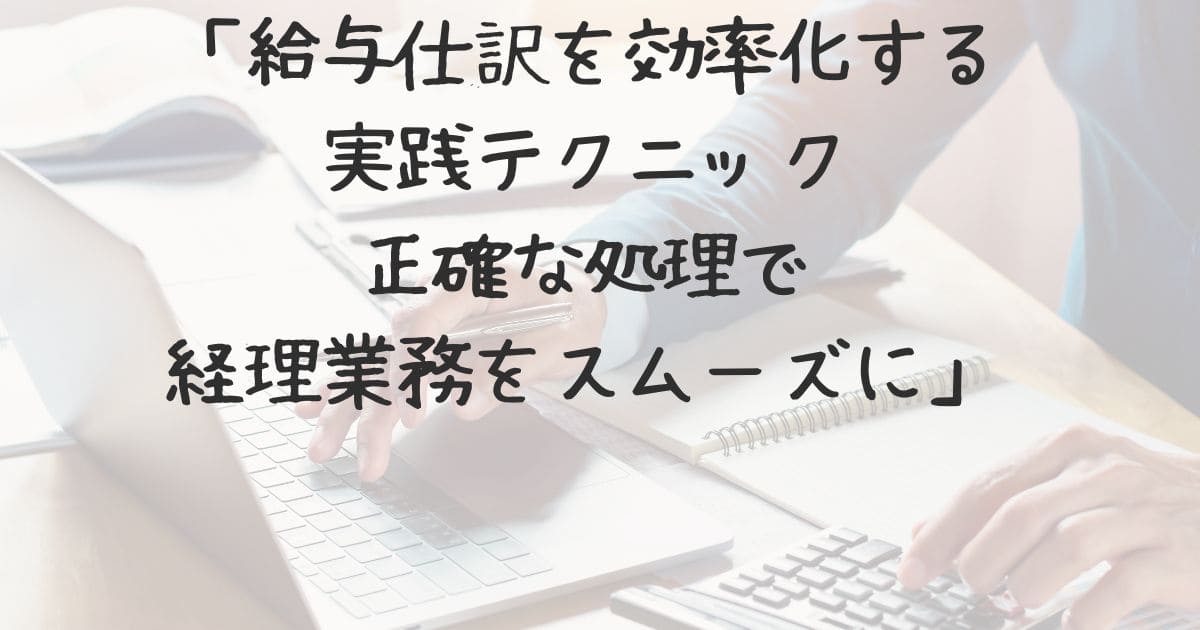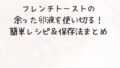給与仕訳の基本を徹底解説|正しい処理で経理精度を高める
企業にとって給与は毎月必ず発生する重要な経費であり、その会計処理は極めて慎重に行う必要があります。
給与の仕訳は単なる支払い記録にとどまらず、税金や社会保険料など複数の要素を含むため、正確な処理が求められます。
適切に仕訳を行えば、帳簿の整合性が保たれ、決算業務や税務調査の際にもスムーズに対応できるでしょう。
給与仕訳を行う際に押さえるべきポイント

給与を仕訳する際は「総額」をまとめて計上するのではなく、控除項目を明確に分けて記録することが基本です。
仕訳は次の3つの要素で構成されます。
-
総支給額:基本給や各種手当など、控除前の金額
-
控除額:所得税・住民税・社会保険料など、従業員から差し引く金額
-
差引支給額:実際に従業員へ支払われる金額(いわゆる手取り)
具体例:給与支給時の仕訳

例として、社員Aさんに対して以下の条件で給与を支給した場合を考えます。
-
総支給額:300,000円
-
所得税:10,000円
-
住民税:12,000円
-
社会保険料:40,000円
手取り金額は238,000円ですが、仕訳では控除額も個別に計上する必要があります。
仕訳例
(借方)
-
給与手当 300,000円
(貸方)
-
預り金(所得税) 10,000円
-
預り金(住民税) 12,000円
-
預り金(社会保険料)40,000円
-
普通預金 238,000円
ここでポイントとなるのは、控除額を「預り金」として処理することです。
これらの金額は会社が一時的に預かり、後日それぞれの機関に納付する義務があるため、正確に記録する必要があります。
会社が負担する社会保険料の仕訳

給与に関しては、従業員からの控除だけでなく会社側が負担する社会保険料もあります。
健康保険・厚生年金・雇用保険など、会社負担分は給与手当とは区別し、別勘定として処理します。
例えば、会社負担分が45,000円の場合は次の通りです。
(借方)
-
法定福利費 45,000円
(貸方)
-
未払金(または未払費用)45,000円
この処理により、会社負担分は「法定福利費」として正確に計上されます。
給与計上時と同じタイミングで処理しておくと、帳簿が整理されやすくなります。
給与仕訳は、各項目を正確に分けて処理することが信頼性の高い会計につながります。
賞与支給時の仕訳と控除処理の正しい方法
給与と同じく、賞与(ボーナス)を支給する際にも正確な仕訳が必要です。
基本的な流れは給与の仕訳とほぼ同様ですが、使用する勘定科目が「賞与」になる点が大きな違いです。
さらに、賞与も各種控除や会社負担分の保険料が絡むため、正確な処理が求められます。
賞与仕訳の具体例

例として、社員に賞与50万円を支給し、控除額として「社会保険料6万円」「所得税2万円」「住民税1万円」が差し引かれ、手取り41万円となるケースを考えてみましょう。
仕訳は次の通りです。
(借方)
-
賞与 500,000円
(貸方)
-
預り金(社会保険料)60,000円
-
預り金(所得税)20,000円
-
預り金(住民税)10,000円
-
普通預金 410,000円
このように、控除された金額は「預り金」として処理します。
会社は一時的にこれらを預かり、後日所定の機関に納付する義務を負います。
会社負担分の社会保険料も忘れずに計上

給与と同様、賞与にも会社側が負担する社会保険料があります。
会社負担分は給与と同じく「法定福利費」として計上し、賞与の仕訳とは別で処理します。
これにより費用の内訳が明確になり、帳簿が整った状態になります。
控除額や会社負担分を納付する際の仕訳

給与や賞与から控除された各種税金や社会保険料は、後日税務署や社会保険事務所などの機関に納付します。
この納付処理も正確な仕訳が必要です。
【納付例】社会保険料40,000円を納付した場合
(借方)
-
預り金(社会保険料)40,000円
(貸方)
-
普通預金 40,000円
会社負担分の保険料を同時に納付する場合は、未払金(または未払費用)から支払処理を行い、残高をゼロにするようにします。
よくあるミスと注意点

賞与や給与の仕訳は複数の科目が絡むため、次のような間違いが起こりやすくなります。
-
控除額を「給与手当」や「賞与」で相殺してしまう
-
「預り金」と「未払金」の区別を曖昧にする
-
会社負担分の法定福利費を計上し忘れる
-
賞与を給与と同一仕訳で処理してしまう
これらの誤りは決算時の整合性を欠く原因となり、場合によっては税務調査で指摘を受ける可能性があります。
帳簿を見た際、誰が見ても明確に仕訳内容が理解できる状態を維持することが重要です。
正確な賞与仕訳を行うことで、経理業務の信頼性が高まり、企業の財務管理もより堅実になります。
給与仕訳を効率よく行うための実務的アプローチ

給与に関する仕訳は、企業にとって毎月必ず行う作業のひとつです。
そのため処理手順を工夫すれば、経理担当者の負担を大きく軽減できます。
ここでは、日々の業務で役立つ効率化の方法を詳しく解説します。
1.会計ソフトと給与ソフトを連携させる
経理業務の効率化にはシステムの自動化が非常に有効です。
freee、弥生給与、マネーフォワードなどの給与計算ソフトを会計ソフトと連携させると、給与計算データから自動で仕訳を作成できます。
- メリット
-
-
手入力が減り、作業時間を短縮できる
-
転記ミスや入力漏れが防止できる
-
会計データがリアルタイムで反映される
-
特に複数の従業員を抱える企業では、手作業から自動化への移行が大きな効果をもたらします。
2. 定型仕訳のテンプレート化
給与の金額や控除が毎月ほぼ同じである場合、定型仕訳をテンプレートとして用意しておくと便利です。
事前にフォーマットを作っておけば、必要な金額だけを変更して登録するだけで済み、入力作業を大幅に簡略化できます。
-
毎月同じ勘定科目を繰り返し入力する手間が減る
-
統一された形式で記録できるため、帳簿が見やすくなる
3. ダブルチェック体制を導入
効率化を進める一方で、誤りの発見体制も重要です。
給与仕訳では、税金や保険料などの金額を間違えると修正に手間がかかり、後処理が複雑になります。
-
月末や月初に第三者による確認を実施
-
金額・勘定科目・控除の内訳を重点的にチェック
-
不明点があれば早期に修正
こうした体制を整えておくことで、ヒューマンエラーを最小限に抑えられます。
まとめ|正確な給与仕訳が会社の信頼性を支える
給与仕訳は単なる数字の入力ではなく、法令や税務処理とも密接に関わる重要な業務です。
-
支給額・控除額・会社負担分を正確に分類して処理する
-
預り金と未払金を混同しないよう注意する
-
定期的な見直しとチェックを行い、精度を高める
これらを徹底することで、帳簿の信頼性が向上し、経営管理や税務対応にも強い体制を築けます。
今回紹介した実務ポイントを参考に、日々の仕訳処理を見直してみましょう。
経理初心者でも、これらを実践すればスムーズかつ正確に業務を進められるようになります。