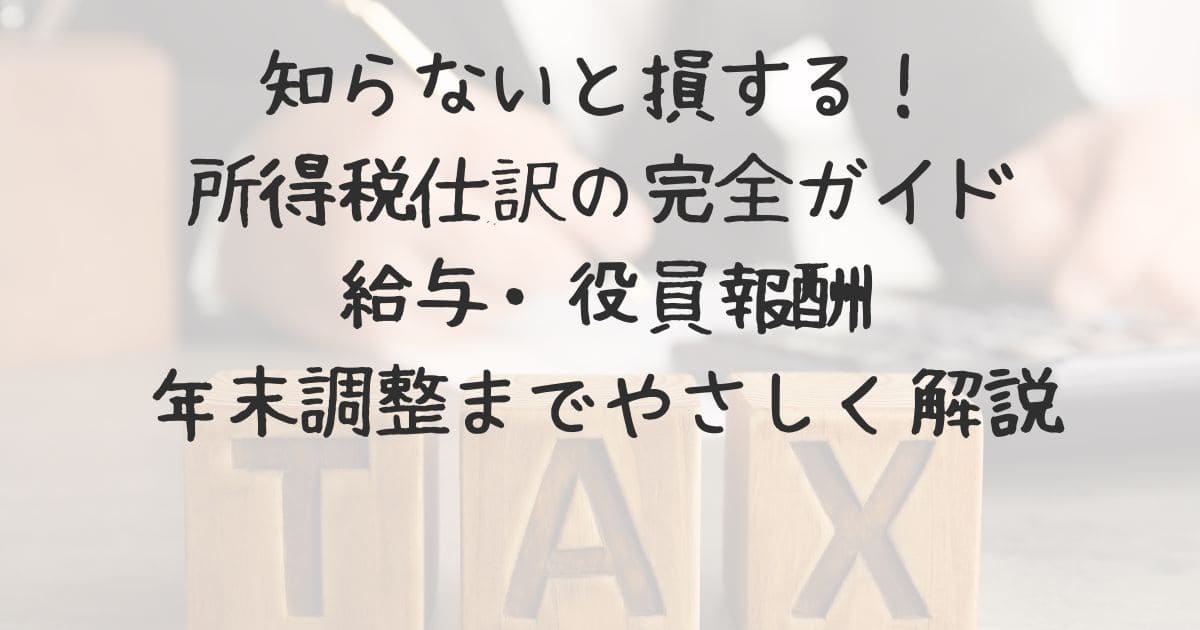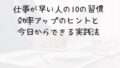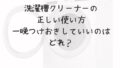所得税仕訳が重要な理由
毎月のお給料や年末調整、役員報酬の支払いなど、会社や事業では必ず発生する「所得税」。
これは事業運営に欠かせない重要な会計処理のひとつであり、正確に仕訳を行うことで税務調査での指摘や追加徴収といったリスクを減らせます。
また、適切な記録は資金繰りや経営判断の際にも役立ちます。
仕訳を怠ると、後から金額のズレや記録漏れが発覚し、修正に時間や手間がかかることもあります。
この記事では、会計初心者さんでも理解しやすいよう、難しい専門用語はできるだけやさしい言葉に置き換え、具体例や流れと一緒に丁寧に解説していきます。
所得税仕訳の全体フローを図解で確認

所得税の仕訳は、大きく分けて以下の流れで行います。
- 給与支給(源泉徴収額の計算)では、従業員ごとの給与額に基づき、国が定めた税率表を使って正しい源泉徴収額を計算します。このとき社会保険料や各種控除も反映させます。
- 源泉所得税の納付は、計算した税額を一定の期限内に税務署へ納付する大切な手続きで、納付方法は窓口・振込・ネットバンキング・e-Taxなど複数あります。
- 年末調整(還付または追徴)では、1年間の所得税額を精算し、多く払いすぎた場合は還付、少なかった場合は追加徴収となります。このときの結果は給与や預り金の仕訳に反映されます。 こうした流れを具体的に押さえておくと、「このお金は給与計算段階なのか、納付段階なのか、それとも年末調整後の処理なのか」といった判断がしやすくなり、経理記録の正確さや作業効率も高まります。
所得税とは?会計処理における役割を理解しよう

所得税は、働いて得たお金に対して国に納める税金です。
給与や報酬といった収入があると、その金額に応じて一定の税率で計算されます。
会社員やパートさんの場合は、給与から自動的に税額が差し引かれ、この仕組みを「源泉徴収」と呼びます。
会社が従業員に代わってその税金をまとめて国に納付するため、従業員自身が毎月納付する必要はありません。
ただし、この仕組みの裏では会計処理が行われており、仕訳では源泉徴収した税額を「預り金」という勘定科目で記録します。
預り金は、一時的に会社が国のために預かっているお金という意味を持ち、納付時にこの残高が減少します。
こうした記録を正しく行うことが、後の税務確認や年末調整でスムーズな対応につながります。
所得税の仕訳で使う主な勘定科目

- 預り金:源泉徴収した税金を一時的に預かっている状態を示します。従業員から天引きした税金は会社の資産でも利益でもなく、国に納めるまでの一時的な負債として扱います。そのため、納付時にこの勘定科目を減らす処理を行います。
- 未払費用:支払日がまだ来ていない経費を表すときに使います。例えば決算時点で給与や賞与が発生しているが支払日が翌期になる場合、この科目で計上しておくと、発生主義の原則に沿った処理ができます。
- 租税公課:会社が直接負担する税金(法人税や事業税など)の記録に使います。源泉徴収税とは異なり、企業自らが納める税金であり、会計上は経費として処理されます。固定資産税や印紙税などもここに含まれ、正しい分類が重要です。
給与支払い時の所得税仕訳

給与支給時の仕訳の流れ
給与を支払うときは、所得税を天引きして、手取り額を従業員に渡します。
天引きした税額は「預り金」に記録し、これは国に納めるまでの一時的な負債として扱われます。
このとき、社会保険料や住民税も同時に控除される場合が多く、給与明細にそれぞれ明記されます。
給与計算ソフトやエクセルのシートを利用すると、税率表に基づいた自動計算ができ、計算ミスを防げます。
仕訳例と金額シミュレーション
例えば、給与が30万円、所得税が1万円の場合:
給与手当 300,000円 / 現金 290,000円
預り金 10,000円この仕訳では、給与手当が総支給額、現金は従業員に渡す手取り額、預り金は天引きした税金の金額を表します。
源泉所得税を納付する際の仕訳

納付時の流れと必要書類
毎月または半年ごとに、まとめて税務署へ納付します。
納付時には納付書の作成や、ネットバンキング・e-Taxでの送金手続きが必要です。
納付書や送金控えは、後日の確認や税務調査での提示に備えて必ず保管しましょう。
仕訳例
預り金 10,000円 / 現金 10,000円年末調整による還付・追徴の仕訳

還付が発生した場合
預り金 ▲5,000円 / 現金 5,000円追加徴収が発生した場合
給与手当 5,000円 / 預り金 5,000円役員報酬と所得税の仕訳

役員報酬も給与と同じく源泉徴収の対象です。
ただし、税率や控除の計算方法、さらに適用される税法の取り扱いに細かな違いがあります。
たとえば、役員報酬はあらかじめ株主総会などで決議された金額に基づいて支払われるため、途中で大きく変動させると損金算入の可否や税務上の扱いに影響する場合があります。
給与と混同して処理すると、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、支給日や金額、計算根拠を明確にして仕訳することが重要です。
個人事業主と法人での仕訳の違い

個人事業主は、自分の所得税を経費としては計上できません。
これは事業主自身の税負担とみなされ、事業経費には含まれないためです。
一方、法人では、従業員や役員の所得税を「預り金」として処理し、後日納付する形になります。
このため、法人は源泉徴収義務者としての責任を負い、毎月または半年ごとに正しい金額を国に納付しなければなりません。
月次処理と年次処理の違い

- 月次処理:毎月の給与支払いと所得税の記録を行います。ここでは給与計算時に源泉徴収額を正しく計算し、預り金として記録することが重要です。また、月次で記録を整理しておくことで、後の年末調整や納付時にスムーズな処理が可能になります。給与や税額の変動がある場合は、その都度記録を更新しておくことがポイントです。
- 年次処理:年末調整や賞与の支給に伴う特別な仕訳を行います。年次処理では年間を通じて徴収した所得税額と実際の税額を比較し、過不足分を精算します。還付がある場合や追加徴収が発生した場合は、それぞれに応じた仕訳を行い、従業員への説明や記録保存も忘れずに行いましょう。
電子申告・納付時の注意点

e-Taxやネットバンキングで納付する場合も、現金や預金の減少として仕訳します。
納付手続きの際は、正しい税額が反映されているか確認し、送金控えや納付完了の画面をPDFなどの形式で保存しておくと安心です。
これにより、後日の税務確認や社内監査でもスムーズに対応できます。
法定調書や納付書作成との関係

法定調書は、年間の支払額や源泉徴収額をまとめた非常に重要な書類で、主に税務署に提出されます。
この書類には、従業員や役員への支払額、源泉徴収した税額、支払い先の氏名や住所などが詳細に記載されます。
作成時には、給与台帳や源泉徴収簿、会計帳簿の仕訳内容と照らし合わせ、一致しているか必ず確認しましょう。
特に数字や氏名の誤り、住所の記載漏れなどは、後の訂正作業や税務署からの問い合わせにつながります。
正確な法定調書は、企業の信頼性を高め、税務対応を円滑にする大切な基盤です。
所得税額を正しく計算するためのチェックポイント

- 税率表を毎年最新のものに更新することはとても大切です。税率や計算方法は法改正によって変更されることがあり、古い表を使い続けると計算ミスや過不足が発生する原因になります。最新版は国税庁の公式サイトなどで確認し、印刷して給与計算や年末調整の際に活用しましょう。
- 扶養控除や生命保険料控除の申告漏れがないか確認することも重要です。従業員が扶養家族の情報を更新していなかったり、保険料控除証明書を提出し忘れたりすると、所得税額が本来よりも高くなってしまいます。年末調整前には申告書の内容をチェックし、不備があれば早めに本人に確認することで、正しい税額計算と円滑な精算が可能になります。
仕訳ミスを防ぐおすすめツール・会計ソフト

クラウド会計ソフトを使うと、自動で仕訳を提案してくれるため、日々の入力作業が大幅に軽減されます。
特に給与や所得税関連の仕訳はパターンが決まっているため、自動提案機能が非常に便利です。
また、仕訳だけでなく納付スケジュールの管理や法定調書の作成サポートなど、付随する機能を備えているものも多くあります。
初心者さんは、まずは無料プランから試して操作感や機能を確認し、自社や事業に合ったプランを選ぶと失敗が少なく安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 所得税と住民税は同じですか? A. 違います。所得税は国に納める税金、住民税は地方自治体に納める税金です。
Q. 賞与の源泉徴収はどうなりますか? A. 賞与は特別な計算方法で源泉徴収します。
まとめ|正しい仕訳で税務対応もスムーズに
所得税の仕訳は、一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な流れとルールをしっかり押さえてしまえば、驚くほどスムーズに行えるようになります。
特に、毎月の給与支給や源泉徴収、納付、年末調整といった一連の流れを理解し、どの段階でどの仕訳を行うのかを整理しておくことが大切です。
また、日々の正しい記録は単に帳簿を整えるだけでなく、税務調査や社内監査における信頼性向上、さらには経営判断の正確さにもつながります。
日常的に記録の整合性を確認し、ミスや漏れがないかをチェックする習慣を持つことで、経理業務全体が安定し、税務対応も安心して行えるようになります。