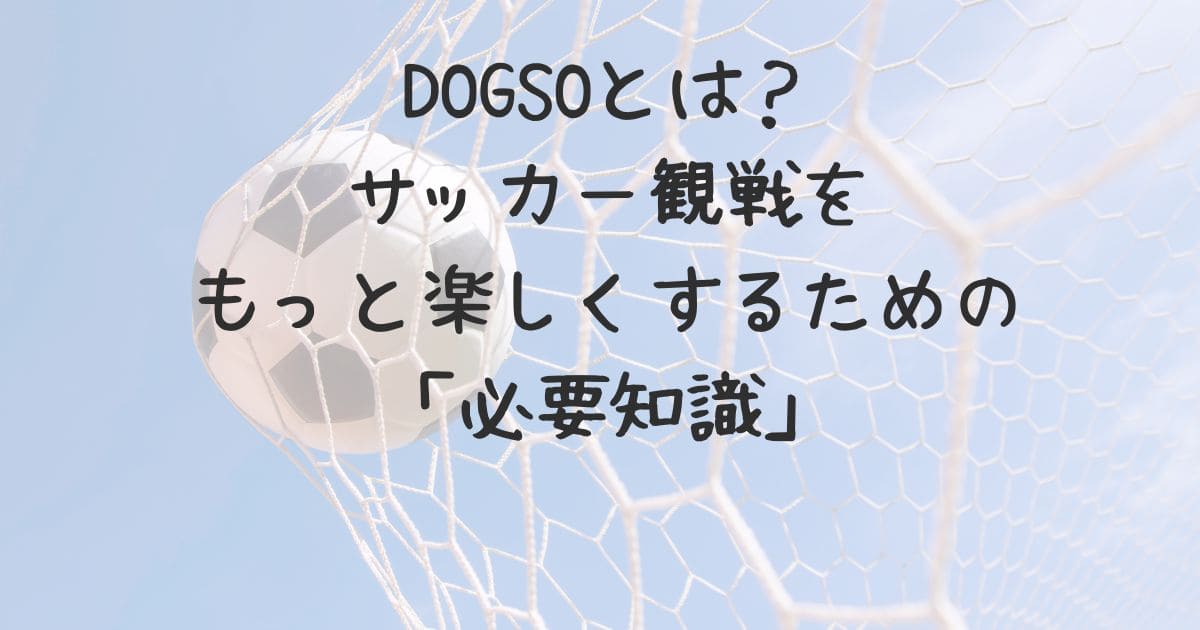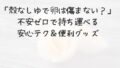サッカーの試合を観ていると、コメンテーターやアナウンサーで「DOGSOだわ」「あれはレッドでしょ」などの声を聞いたことがありませんか?
最近は画面にもカード色やコメントが出ることが増え、観戦中の状況がわかりやすくなっていますが、DOGSOはそれと同時に「わかりにくさ」につながる用語の一つでもあります。
この記事では、DOGSO(ドグソ)とは何なのか?から、レッドカードにならない場合や、SPAとの違い、実際の別の試合での判定例まで、やさしくご紹介します。
さらに、ルールの変遷の経緯や、誤解しやすいポイントなどもまとめて、観戦がもっと楽しく、サッカーが近くなるような内容になるよう尽力をそぎました。
「ルールよりも、体感で理解したい」という方も、「もっと観戦の時間を楽しみたい」という方も、ぜひ最後までお読みくださいね。
DOGSOの意味とは?基本からわかりやすく解説

まず、DOGSOは「Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity」の略語で、日本語では「決定的な得点機会の阻止」という意味になります。
サッカーでゴールに直結しそうなプレーを、明らかに不正な方法で止めてしまった場合に適用されるルールです。
たとえば、攻撃側の選手が相手ディフェンダーをかわしてキーパーと1対1になり、あとはシュートを打つだけという状況で、背後から足をかけられて倒される場面を想像してみてください。
このように、ゴールの可能性が非常に高かったプレーを妨害されたと審判が判断したときに、DOGSOが適用されるのです。
また、手を使った反則(意図的なハンド)によってボールの進行を止めたり、相手選手の進路を妨げたりするケースでもDOGSOとなることがあります。
「得点のチャンスを潰された!」というような場面ですね。
選手が一人でゴールに向かっているときに、後ろからタックルされたり、手で止められたりすると「DOGSO」が適用される可能性が出てきます。
このルールがあることで、守備側の選手がルールを無視して強引に止めにいくことを防ぎ、試合の流れやフェアプレーの精神を守る役割を果たしています。
得点機会を大切にするサッカーらしいルールのひとつなんですよ。
DOGSOが成立する4つの条件とは?

DOGSOの判定には、次の4つの要素がポイントになります。
- ボールの方向:反則時、ボールはゴールに向かっていたか?
- たとえば選手が斜めに走っていたとしても、明らかにシュートを狙える方向であれば、これは重要な要素になります。
- 選手の位置:攻撃側の選手がボールをコントロールできていたか?
- 足元にしっかりボールがあるか、それともバウンド中かで印象が変わります。次の動きがスムーズにできるかも判断材料なんです。
- 守備選手の数:最後の1人の守備選手による反則だったか?
- 他に守備の選手がいたとしても、明確に止められなかった位置にいた場合は「最後の壁」としてDOGSOの対象になります。
- 反則の内容:明らかな得点機会を反則で妨げたかどうか?
- これはタックル、手での接触、ユニフォームを引っ張るなど様々ですが、審判の裁量が大きく影響する要素です。
この4つを総合的に見て、審判が「明らかな得点チャンスを不当に止めた」と判断すれば、DOGSOが成立します。
審判は一瞬の状況を見極めながら、これらすべてを踏まえて判断しているんですね。
逆にいえば、1つでも要素が欠けていたり、曖昧だと判断されれば、DOGSOとは認められず、軽度な反則(たとえばSPA=有望な攻撃の阻止)として扱われることになります。
そのため、観ている私たちからすると「なんでレッドじゃないの?」と思う場面でも、実はルール上はイエロー止まりだったりすることもあるんですよ。
DOGSO=レッドカードとは限らない?意外と知らない“軽減ルール”とは

実は、「DOGSO」と判定されても、必ずしもレッドカードになるとは限りません。
少し前まではDOGSO=即退場という印象が強かったのですが、近年のルール改正によって、その判断は少し柔軟になってきています。
特に、ペナルティエリア内でのファウルに関しては、「正当なチャレンジ」と判断されれば、イエローカードに軽減される場合があるんです。
たとえば、相手のボールを取りにいこうとした中で結果的にファウルになってしまった場合。
そのプレーが故意ではなく、スライディングなどでボールに向かっていたと認められたときは、PK+イエローで済むケースもあります。
このルールの背景には、「PKも与えて退場もさせるのは重すぎるのでは?」という声があったからです。いわゆる“ダブル・ペナルティ問題”ですね。
そのため現在では、意図的でないプレー、つまり純粋にボールを奪おうとしたチャレンジであれば、DOGSOでもレッドにはならない可能性があるのです。
ただし、手や腕を使ったり、進路を完全にふさいでしまうようなプレー、または背後から押すなどの悪質な行為は「正当なチャレンジ」とは見なされず、レッドカードの対象になります。
このようにDOGSO=レッドカード、というイメージは徐々に変化してきていて、審判はその都度「プレーの意図」や「状況の緊迫度」も考慮しながら判断しているんですね。
次は、よく混同される「SPA(エスピーエー)」との違いについて見ていきましょう。
DOGSOとSPAの違いとは?混同しやすい2つの反則を整理しよう

サッカー観戦をしていると、「DOGSOかと思ったらSPAだった」というような解説を耳にすることもあるかもしれません。
どちらもファウルに関する用語ですが、意味や適用される場面が異なります。
まず、SPAとは「Stopping a Promising Attack」の略で、「有望な攻撃の阻止」という意味です。
DOGSOほど決定的ではないけれど、それなりに得点のチャンスがあった場面での反則に対して使われます。
たとえば、相手の選手がドリブルで抜け出そうとしている場面で、守備側がちょっとユニフォームを引っ張ってスピードを落とさせた──こういったプレーがSPAに該当するケースです。
一方でDOGSOは、もっと明確に「これを止められなければほぼゴールだった」というようなシーンに適用されるものです。
つまり、SPAは“可能性のある攻撃”を止めたもの、DOGSOは“明確なゴール機会”を止めたもの、という違いがあります。
SPAの罰則は基本的にイエローカードです。一方でDOGSOは、前述のように状況によってレッドかイエローになります。
この違いを知っておくと、「なぜこのファウルでカードの色が違ったのか?」という疑問が減り、より深く観戦を楽しめるようになりますよ。
次は、実際の有名なDOGSO判定の例を見ながら、より具体的に理解を深めていきましょう。
有名なDOGSO判定の実例をチェック!あの場面は本当に正しかったの?

実際の試合でDOGSOが話題になったケースを見てみると、ルールがどう適用されたのかがより明確に理解できます。
たとえば、日本代表がメキシコ代表と対戦した国際親善試合での場面。日本の選手がゴールに向かって走っていたところ、相手DFに倒されました。
一見、DOGSO=レッドと思いきや、審判の判断はイエローカード。
SNSでは「なんでレッドじゃないの?」「完全に1対1だったのに」といった声が飛び交いましたが、実はこの場面、ボールの方向がややゴールから逸れていたことと、後方からカバーに入れる味方選手がいたことで、DOGSOの条件をすべて満たしていないと判断されたのです。
このように、DOGSOの適用はとても繊細。たった1つの条件が欠けるだけで、カードの色も、試合の流れも大きく変わるのです。
次のセクションでは、こうした判断が観戦の楽しみ方にどう影響するのか、ルールを知ることの面白さについて深掘りしていきます。
DOGSOのルールを知ると観戦がもっと楽しくなる理由

サッカー観戦は、ただ「ゴールが決まった」「勝った・負けた」だけではなく、その裏にある細かなルールや駆け引きを知ることで、より奥深く楽しむことができます。
DOGSOというルールはまさにその代表格。なぜあの選手が退場になったのか、あるいはなぜイエローで済んだのかがわかるだけでも、試合の見方が一気に広がります。
特に注目すべきは、審判が下すカードの色の意味です。
「レッドかイエローか」の判断は、その瞬間の状況判断だけでなく、ルールに基づいた冷静な分析によって導き出されています。
そこには一瞬のプレーを見極める集中力と、的確なルールの知識が欠かせません。
観戦者としても、DOGSOの成立条件や軽減規定を知っておくと、「あ、これはDOGSOかも?」と自分で推測しながら試合を楽しめるようになります。
そして自分の予想と審判の判断が一致したときの納得感や、逆に食い違ったときのモヤモヤ感もまた、観戦の醍醐味のひとつと言えるでしょう。
サッカーのルールはときに難解に感じられるかもしれませんが、「知れば知るほど面白くなる」のもまた事実。DOGSOはその入口としてぴったりのテーマです。
試合の流れが変わる“決定的な瞬間”に注目しながら、次の試合ではぜひ「DOGSO目線」で観てみてくださいね。
【おさらい】DOGSO理解度チェック!あなたならどう判定する?

最後に、これまで学んだ内容をもとに、実際のプレーをイメージした「DOGSOクイズ」に挑戦してみましょう。
Q1:攻撃側の選手がゴールキーパーと1対1でシュート体勢に入りました。そこへ後方から守備選手がスライディングタックルを仕掛けて倒しました。審判はPKを与え、守備選手にイエローカードを提示。この判定、妥当?それともDOGSOでレッド?
→**正解:状況によるが、軽減ルールが適用された場合はイエローカードで妥当。**もし守備側がボールを奪おうとした正当なチャレンジであったと判断されれば、DOGSOでもイエローに軽減される可能性があります。
Q2:センターライン付近で、明らかに得点の可能性がありそうなドリブル突破をユニフォームを引っ張って止めた。相手ゴールまではまだ距離がある。これはDOGSO?
→**正解:DOGSOではなくSPA。**この場合は「有望な攻撃の阻止」としてSPAが適用され、通常はイエローカードとなります。
このように、DOGSOとSPAを見分けるには「プレーの位置」「守備選手の数」「ボールの方向」など、複数の要素を総合的に見る必要があります。
観戦中に「これはDOGSO?SPA?」と考えながら観ることで、ルール理解も深まり、サッカーがもっと好きになるはずです。
まとめ|DOGSOを知ると“サッカーの奥行き”が見えてくる
いかがでしたか? DOGSOというルールは、ただの反則名ではなく、サッカーの魅力やドラマを生み出す重要な要素のひとつです。
「なぜその選手が退場になったのか」「どうしてあの場面ではカードが出なかったのか」──そんな疑問も、DOGSOの基本を知っていればきっとスッキリ理解できるようになります。
ぜひ次の試合では、カードが出る場面に注目してみてください。「これはDOGSO?それともSPA?」そんな視点が持てるだけで、観戦の楽しみ方がグッと広がりますよ。
サッカーをもっと深く楽しむ第一歩として、DOGSOルールを味方につけてくださいね!