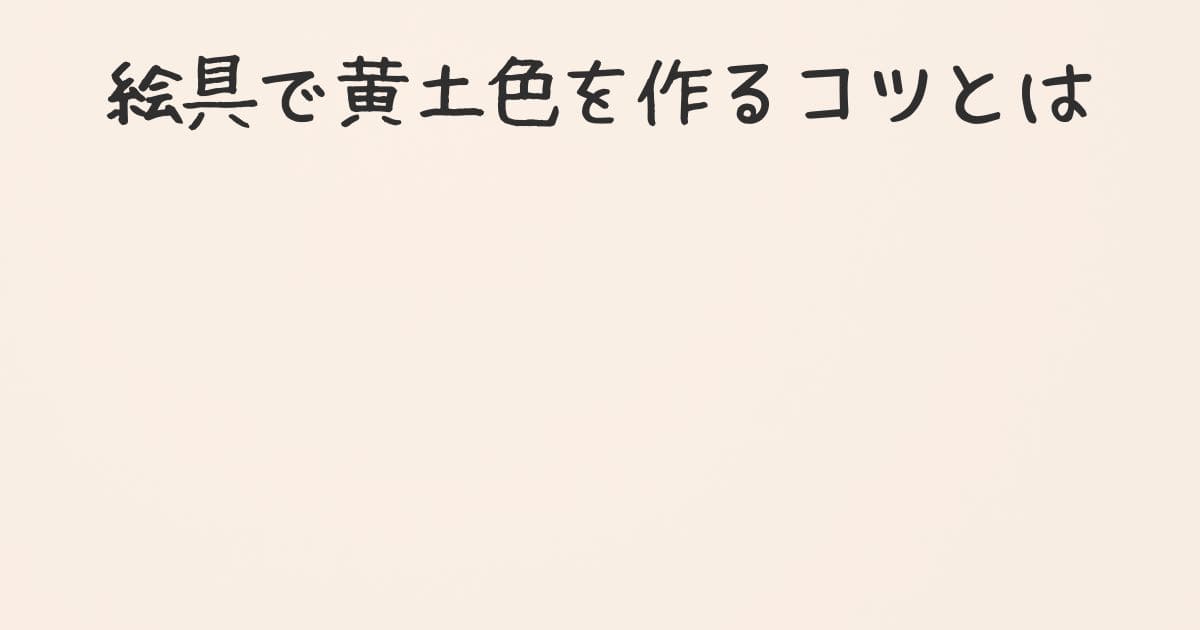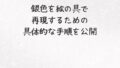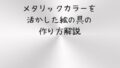絵画やイラストにおいて、温かみや自然の風合いを演出するために欠かせない「黄土色(おうどいろ)」。
一見地味に見えるこの色ですが、肌の表現や風景の背景、建造物の質感など、幅広い場面で活躍する非常に便利な中間色です。
しかし、市販の黄土色では表現しきれない微妙なトーンやニュアンスを必要とする場面も多く、自分で混色して黄土色を作り出せるスキルは作品表現の幅を大きく広げてくれます。
この記事では、絵具を使って黄土色を自在に作るための基本的な混色テクニックから、アクリルや色鉛筆など様々な画材ごとの表現方法、さらには明度・彩度の調整方法や応用例までを詳しく解説します。
初心者から上級者まで、あらゆるアーティストに役立つ内容を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
黄土色の作り方を知ろう

黄土色とはどんな色か
黄土色は、地面や土壌を思わせるような、黄色がかった落ち着いた色みを持つ色合いです。
オーカーな土の赤みを含んだアースト色にも近く、大地や自然を表現するのに適した色と言えます。
中間色としての性質もあり、周囲の色によって印象が変化しやすいため、絵画においては非常に扱いやすい色でもあります。
特に風景画や静物画などで空間のつながりを自然に演出したい場合には、重宝される存在です。
絵の具で黄土色を作る重要性
黄土色はパレットとして使えるだけでなく、人物画の肌色、風景画の地面、レトロ、化石などにも広く応用できます。
特定の黄土色がなくても、混色で自由に作り出せると表現の幅が広がります。
市販の黄土色では微妙なトーンの調整が難しい場合もあるため、自分で色を作ることができれば、意図した通りの作品づくりが可能になります。
さらに、限られた色数で多彩な表現を行うトレーニングとしても、混色による黄土色づくりは効果的です。
黄土色と三原色との関係
黄土色は、ベースになる三原色「赤」「青」「黄」の絵の具を適切な比率で組み合わせることで作れます。
色彩理論においては、これら三原色の掛け合わせによって自然界に存在するほぼすべての色を生み出せるとされており、黄土色もその代表例のひとつです。
混色時の微調整によって、よりリアルで深みのある土の質感を表現することが可能になります。
黄土色の基本的な作り方

必要な絵の具のセット
基本的には「黄色」「赤色」「青色(緑)」を用意します。
基本の混色方法
- 黄色を基盤にする
- ごく少量の赤色を加える
- さらに少量の青色を加えて色みを正す
色の調整と比率
黄:赤 = 3:1 の比率から始め、当たりを見ながら青色をわずかに加えるのがポイントです。
黄土色のバリエーションを楽しむ

薄い黄土色の作り方
基本の黄土色に白色を添えることで、薄くなり、より軟らかな印象になります。
白色を加える割合を増やすことで、まるでパステル調の柔らかい色合いを作ることができ、やさしさや清潔感のある表現に適しています。
また、水彩絵の具の場合は水の量を増やすだけでも薄い黄土色が再現できます。背景や空気感を演出したいときに便利なテクニックです。
深みのある黄土色を作る方法
赤色や褐色、茶色を加えていくと、深みと広がりのある色みになります。
特に焦げ茶やバーントシェンナのような濃い色を加えることで、落ち着きや重厚感を表現することができます。
暗めの色を少量ずつ重ねていくことで、奥行きのある色彩が完成し、風景画の山肌や歴史的建造物の表現にぴったりです。
補色を使った色合いの調整
青系の色をわずかに加えると、はっきりしたアンダートーンを減らし、まろやかな色みになります。
補色関係にある青や緑をほんの少し加えることで、黄土色の黄味を和らげ、より中立的で落ち着いた色合いに変化させることができます。
陰影やニュアンスを加える際に便利で、特に光と影のグラデーションを自然に見せたいときに効果を発揮します。
様々な画材での黄土色の作り方

アクリル絵の具での作り方
基本の黄色・赤色・青色を経済し、自由に混ぜられるのがアクリル絵の具の利点です。
アクリルは乾きが早く重ね塗りがしやすいため、色の微調整や立体的な塗りにも向いています。
筆で大胆に塗っても、乾いたあとにさらに別の色を重ねられるのが特徴で、黄土色の深みやグラデーションを表現するのに最適です。
透明メディウムを加えることで、さらにコントロール性を高めることもできます。
クーピーや色鉛筆での表現
黄、赤、褐系の色を重ねるように塗り込むことで、簡易な黄土色を再現できます。
まずは黄色をベースに敷き、次に赤を軽く重ね、最後に茶系や褐色系の色を用いて深みを出します。
筆圧を変えたり、色をこすり合わせたりすることで微妙なニュアンスも演出できます。
さらに白や灰色を加えることで、明るさや彩度をコントロールすることも可能です。
ポスターカラーで実現する黄土色
色の赤みや黒みを見ながら、カラーを重ねてつくります。
ポスターカラーは発色が鮮やかで隠蔽力が高いため、はっきりとした黄土色を作りやすい画材です。
ベースとなる黄と赤の混色に少しずつ黒を加えることで、重厚感のあるトーンを表現できます。
水を少なめに使うことで濃密な色合いに、逆に多めに使えば透明感のある仕上がりにも調整できます。
黄土色の彩度と明度を調整する

明度を高めるための工夫
白色を加えることで、色みが軟らかに、ところどころに光の印象を与えます。
彩度を落とすための混色法
灰色や褐色、ごくわずかな青色を加えて、彩度を下げるのも有効です。
黒色や白色との比率
黒色は少量でも色を大きく変えてしまうので、非常に少しづつ試すことが重要です。
特定の色を使った黄土色の作り方

赤色と黄土色の相性
赤色を加えると、なめらかな印象を持たせます。
さらに、赤の種類によっても与える印象が変わります。
たとえばカドミウムレッドのような鮮やかな赤を使えば温かみが強くなり、バーントシェンナを加えることで落ち着いた雰囲気を作ることができます。
赤を加える割合を微調整することで、肌の血色や秋の紅葉を思わせる暖色トーンの黄土色に変化させることも可能です。
青色や緑色を混ぜるとどうなるか
青色は彩度を落とし、大地的な風合いを形成します。
特にウルトラマリンブルーなどを少量加えると、やや冷たくくすんだトーンになり、影や遠景の表現にも適した黄土色が完成します。
また、緑色を加えることで土に苔や植物が混じったような自然なトーンが生まれ、森の地面や湿地帯の風景にぴったりの表現になります。
青・緑ともに加える量には注意が必要で、わずかな違いで印象が大きく変わるため、少しずつ加えて様子を見ましょう。
茶色も取り入れた色合いの実験
茶色は色みを複雑にし、黄土色に課題性や地球感を加えます。
特にバーントアンバーやローアンバーなどの茶系絵の具を使うと、落ち着きのある渋い黄土色が生まれます。
絵画の中で年季を感じさせる木材、枯葉、岩肌といった対象物を描く際にも効果的です。
さらに茶色をベースにしたうえで微量の赤や黄を加えれば、気候や光の状況に応じたカラーバリエーションも自在に作ることができ、よりリアルな風景描写につながります。
まとめ
黄土色は、絵画表現において自然さと落ち着きをもたらす大切な色のひとつです。
三原色を基本とした混色により、自分好みの黄土色を作り出すことは決して難しくなく、画材や目的に応じた調整によって、幅広いニュアンスを表現することが可能になります。
アクリルやポスターカラー、水彩、色鉛筆など、使用する画材ごとに工夫を凝らし、明度や彩度、補色の扱い方を理解することで、より奥行きのある仕上がりが期待できます。
今回ご紹介した方法を参考に、あなただけの理想の黄土色を見つけ、作品づくりに活かしてみてください。表現の可能性がさらに広がるはずです。